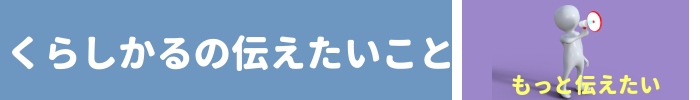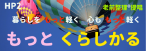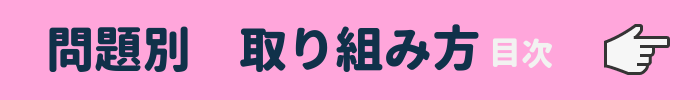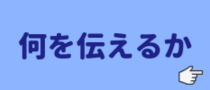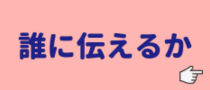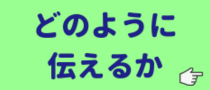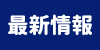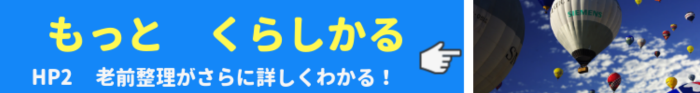老前整理 片づけ 講演 終活 シニア 行動経済学 ひとり暮らし ロボット
【どのように伝えるか】
どのように伝えるかが、くらしかるの考えてきたことです。
対象、場所、媒体、伝え方と試行錯誤をしながら歩んできました
 |
大阪市のインキュベーションオフィスに入居できたことからすべてが始まりました |
2006年9月 クレオ大阪(財団法人大阪女性協会) チャレンジオフィス入居
2007年5月 株式会社くらしかる設立
2008年9月 クレオ大阪北チャレンジオフィス卒業 スペースここから(浪速区)入居
2008年9月〜10月 「家族を介護する女性のためのライフアップセミナー」主催
2008年9月〜11月 尼崎市女性センタートレピエ カラーコーディネーター
2・3級受験対策講座
2008年11月〜12月 東淀川区役所主催 地域協働プロジェクト
「介護家族のための気持ち★リフレッシュ講座」全4回
2009年1月 クレオ大阪北 経営セミナー 講演
2009年7月 福in亭「桂雀喜落語会」企画
2009年8月 クレオ大阪女性総合相談センターオープニングフェスタ
「こども落語家入門][落語って面白いやん!!」企画
2009年9月 クレオ大阪中央主催 「がんばりすぎない老親介護」
〜転ばぬ先の知恵+気持ちリフレッシュ〜 担当
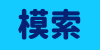 |
どうすれば老前整理を伝えられるかわからず、模索の時代 |
▼2009年2月17日 ブログ小説「わくわく片付け講座」執筆

2010年2月まで1年間毎日書きました。最後が26章、つまり26の話を書きました。無知とは恐ろしい。当時は出版の世界のことも何もわかっていなかったので、この小説を本にして出せたら…と、今考えたら、とても恥ずかしいことをまじめに考えていました。(このブログは現在削除しています。)
ただこの時は自分の中で、老前整理をする時にどのようなことが起こるかという「シュミレーション」をしていたような気がします。この中の「片付かないから離婚」が2011年に創作落語の元になっています。
上の画像はブログ小説のトップページ アクセス数が一桁のこともあったブログでした。
小説 老前整理 「わくわく片付け講座」を加筆修正して2019年1月28日よりHP2に掲載しています。目次と「なぜ、小説 老前整理を書いたのか」について↓HP2
▼2009年9月 老前整理コンセプト完成 「老前整理」商標登録申請
悩んだ末、将来に備え?「老前整理」の商標登録をしておこうと思いました。
 |
あとから振り返ってみて、それまでの流れが変わったと思うきっかけは、このCBビジネスコンペでグランプリを受賞したことだと思います |
▼2009年12月 大阪市CBビジネスプランコンペでグランプリ受賞
授賞式のあいさつで喜びのあまり「老前整理を全国に広めたい」と口走り、引くに引けな
くなりました。
▼2010年1月 老前整理のセミナー開始
はじめは人が集まらず、受講者が5人の時もありました。
▼2010年11月 落語 老前整理「片付かないから離婚」DVD制作
出演は落語家 桂 雀喜師匠(桂米朝事務所)、坂岡も10分ほど老前整理について話をしています。背広を処分できない男性に向けて、洋服を捨てられない女性を通し、自分自身のことを顧みてほしいと思い制作しました。(創作落語)今考えると、一番初めに落語とは!?無謀でした。DVDの一部をYouTubeでご覧いただけます ↓  http://youtu.be/WSPXqmvIMp0
http://youtu.be/WSPXqmvIMp0
 http://youtu.be/WSPXqmvIMp0
http://youtu.be/WSPXqmvIMp0 |
思いがけないチャンスから『老前整理』を出版し、本格的に老前整理を提唱 |
▼2011年1月 『老前整理』徳間書店刊
 |
老前整理について書いた初めての本です。表紙のデザインは女性向けでピンク。「老前整理」という言葉にインパクトがあるということで、このようなデザインになりました。 この本は朝日新聞の取材を受けたことがきっかけで実現しました。ラッキーだったと思います。この本を出すときに考えていたことを書いた文章です。→『老前整理』出版について |
▼2011年5月〜7月 コラム「やってみよう老前整理」時事通信社から全12回配信
| 2011年5月30日付 京 都新聞 夕刊 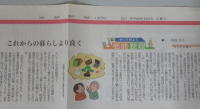 |
新聞にコラムを書くという思いがけない仕事をいただき、おっかなびっくりで書き始めました。京都新聞をはじめ、全国の新聞社に配信いただき掲載されました。親しみやすいイラストは、むらかみちおり氏が担当してくださいました。 この仕事がのちの東京新聞などのコラム連載につながったと思っています。 本を読むには「買う」か、「図書館で借りる」という行動が必要ですが、新聞に載ればそのようなハードルがなく、読んでいただけるので老前整理を知っていただくチャンスだと思いました。 |
▼2011年9月 『老前整理実践ノート』徳間書店刊
 |
老前整理は自分で頭の整理と心の整理をしてものの整理を奨めていますから、読者の要望もあり頭の整理のために自分で書き込めるノートを作りました。 1冊目の『老前整理』とイメージを共有したデザインで、中の活字も大きくなりました。 (この本が後に、「老前整理」と共に、NHK学園通信教育「やってみよう老前整理」のテキストになりました) |
▼2012年4月 『老前整理をはじめてみれば』
 |
販売は全国の生活協同組合のみです。生協のカタログに本が掲載され、申し込めば家まで届けてもらえます。この本はネットで本を買えない、近くに書店がない、もしくは書店に行けない(近くに書店がない)、つまりある意味、本の「買い物難民」向けに書きました。だから書店には並んでませんし、アマゾンにも新本は挙がっていません。この本の編集者とは、多くを売るベストセラーよりロングセラーを目指そうという話をしました。 おかげさまで2018 年に6刷になり、販売していただいています。 PHPエディターズ ■生協のみの販売です。(PHP社の通販では購入可) |
 |
東京新聞コラム開始、読者に具体例で老前整理を啓蒙したい! |
▼2012 年10月10日〜2015年9月23日 「坂岡洋子の1,2の老前整理」コラム
| 2012年10 月10日付東 京新聞  |
東京新聞・中日新聞に掲載。(イラストなかだえり氏)月2回担当させていただきました。連載で少しずつ老前整理について知っていただくのと、身近な具体例を紹介し、ご自分の身に置き換えていただけるとやりがいがあると思い、書いていました。このコラムをまとめ、加筆したものが2016年に『転ばぬ先の老前整理』になりました |
▼2012年12月 『日本一親切な老前整理』 主婦と生活社
 |
老前整理を始めたきっかけは介護の現場でものが多すぎると思った事です。ですから介護を受けるようになる前にという警鐘を伝えたい。しかし重く、深刻にならないように一部4コマ漫画を入れてクスッと笑える「高齢者あるある」の実例で訴えたいと思った本です。 (サザエさんを目指したのですが…) |
 |
NHK学園で「やってみよう老前整理」通信教育レポート添削 40代~90代と幅広い年齢層の方が受講してくださいました |
▼2013年2月〜2016年4月 NHK学園通信講座「やってみよう!老前整理」講座担当
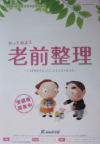 |
受講者1183人。通信講座なので、2回のレポートを提出していただき、添削する形ですが、実際は問題やお悩みなどについての相談をお受けするような形が多い講座でした。 (テキストは『老前整理』と『老前整理実践ノート」使用) 通信講座の受講者の感想は『老前整理』文庫版あとがきに紹介 |
▼2013年4月27日〜2016年3月21日 「坂岡洋子の暮らしかる」コラム
| 2013年4月 27日付毎日 新聞  |
毎日新聞に掲載。月1回担当させていただきました。老前整理という限定ではなく、暮らしを軽くするというテーマでした。この「くらしかる」をひらがなにするか(弊社の社名になる)「暮らし」と漢字にするか検討され、漢字になりました。 |
▼2014年2月 『定年男のための老前整理』徳間書店
 |
男性と女性では、もの整理について考え方が違う。ひとくくりにはできないので、タイトル通り定年を意識した男性向けに書きました。表紙のデザインも当然、男性向けの黄緑色です。イラストも男性のイラストレーターが描いてくださいました。自分史年表付 妻に嫌われる夫と、妻に頼られる夫の違いはどこか? 知りたくありませんか |
 |
NHKラジオ第2放送 こころをよむ講座担当 全国のリスナーへ発信。講演のようにパワーポイント(絵や写真)を使わずことばだけで伝えるのに苦労しました |
▼2014年4月〜6月 NHKラジオ第2 こころをよむ
『心と暮らしを軽くする「老前整理」入門』 NHK出版 ムック
 |
ラジオでの講座はこの時がはじめてで、老前整理について13回お話ししました。本や新聞の読者とは違うラジオを通して、リスナーに老前整理を知っていただきたいと思いました。この時、テキストを書き、毎回40分(CMなし)話をすることの大変さを痛感しました。ムックは雑誌扱いで、完売しました。 |
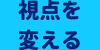 |
老前整理が必要だと感じたのは介護の現場です。原点の介護の問題を考えることで、老前整理の違う面、対象も見えてくるかと思いました |
▼2014年10月 『老いた親とは離れなさい』朝日新聞出版
 |
唯一、老前整理と違い、介護をする家族のための本です。たまたま編集者からこの企画をいただきました。当時は介護される人についての本が多かったので、介護をする側に立って書きたいと思いました。なぜなら周囲で働きながら家族の介護をして、倒れる寸前の人がたくさんいたので、共倒れにならないように読んでもらいたいと思いました。表紙はやさしいデザインになりました。 なぜこのような本を書いたかはこちらの「はじめに」ご覧ください。 |
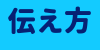 |
単行本と新書、文庫本では読む層が違うことがわかり、老前整理を広めるため 読者層を広げたいので新書や文庫で伝えることにしました |
▼2015年2月 『老前整理のセオリー』 NHK出版
 |
初めての新書です。『定年男の老前整理』の単行本よりも男性には手に取っていただきやすいかと思いました。この本では実家の片づけや空き家問題など、老前整理以前で、働いている男性にとって興味のある問題から取り上げました。 |
▼2015年8月 『暮らしの豆知識2016』 セカンドライフを楽しむ 担当
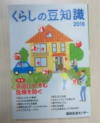 |
国民生活センターは、法律によってつくられた、消費者のための国の機関です。くらしをよりよくするために、全国の消費生活センターと協力してくらしに役立つ情報を提供しています。「老前整理」がそのような、くらしに役立つ知識として認められたようで、見開き2ページですが原稿依頼をうれしく思いました。 |
▼2016年5月 『老前整理』新潮文庫
 |
2011年の『老前整理』(徳間書店)の文庫版です。ピンクの単行本では楽しいイラストをたくさん入れていただきましたが、対象読者が変わるので、文庫ではイラストなしの文章のみで表紙のデザインも、気力体力のキーワードからエネルギーの湧く黄色です。残念ながら3年間の限定発売で2019年3月末で新刊の販売は終了しました。 |
▼2016年12月 『転ばぬ先の老前整理』 東京新聞
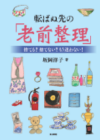 |
東京新聞・中日新聞に連載のコラム「坂岡洋子の1,2の老前整理」をまとめ、加筆したものです。「老前整理あるある」と具体的なものの片づけ方などの実例集です。新聞のコラムを切り抜いて溜めてくださっているという方もあり、読みやすいようにまとめ、3分の1くらいは新しく加筆しました。表紙の絵はコラムのイラストを描いてくださった、なかだえり氏にお願いしました。 |
 |
長年抱えていた頭ではわかっているのに「なぜ捨てられないのか」の疑問の答えとしてたどりついたのが「行動経済学」でした |
▼2018年4月〜6月 NHKラジオ第2放送 こころをよむ『老前整理の極意』
 |
この講座の担当は2回目です。そのまま同じ話をするわけにはいきませんので悩みました。また初めて聞いてくださる方もあります。そこで老前整理の基本的なことは残し、「行動経済学」や「老前整理の裏メニュー」など新しい項目を入れました。テキストを書いたり、この講座の準備におよそ1年半かかり、もう辞めたいと思った事が何度もあり、私にとっては大きなチャレンジでしたが、このような機会でもないと、できないことばかりでした。 |
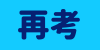 |
それまで気になっていた疑問が行動経済学で解け、あと老前整理に足りないものを考えると「ひとり暮らしの老前整理」でした。この点を仕事の棚卸をしながら、ホームページを1冊の本のようにしようと思い立ちました。具体例その他、老前整理のことがわかるようにリニューアルを考えて作業を始めましたが、ページ数が多すぎるてわかりにくい。そこで新企画のための2つ目のホームページ「もっと くらしかる」を作ることにしました |
▼2018年7月〜2019年5月 新ホームページ作成
|
|||
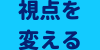 |
「ひとり暮らし」が超高齢社会に向けてのポイントになると思い、ものを片付ける以前に、ひとり暮らしの質を考えることが結局は老前整理につながると思いました。そこで重要なのはコミュニケーションです |
▼2018年7月〜2019年3月
ひとり暮らしの高齢者のコミュニケーション力向上について、考えていました。NHKラジオ第2「こころをよむ」の2回の放送でも「ひとり暮らし」について取り上げていましたが、これだ! という方法は提案できず、突破口を探していました。
 |
コミュニケーションの一助としてたどり着いたのが予想もしなかったロボットとの出会いです。2019年4月のバリアフリー展でひとめぼれというか、見て、機能を知り、これだと思いました |
▼2019年4月〜 ひとり暮らしのロボット作戦開始
| イラスト よしだみさこ氏  |
講演活動以外に、女性向け、男性向け、単行本、マンガ、新書、実例集と、対象によりどうすれば老前整理を伝えられるかを考えてきました。試行錯誤のうちに出会ったのがロボットみらくる(ロボホンというスマートホン)です。このロボットとのコミュニケーションをただいま実験中です→HP2ロボット作戦 現在はココ ただロボットとコミュニケーションをするだけでなく、その先のことも妄想中、乞うご期待! |
▼数年後
 |
ひとり暮らしのロボット作戦が実現すればようやく各論が終わり、「老前整理」の全体像が見えてくると思っています |
 |
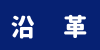 |
 |
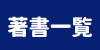 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
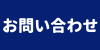 |
 |
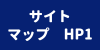 |
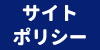 |
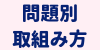 |
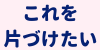 |
このHP1では伝えきれない! ⇒ もっと くらしかる HP2 は 
 |
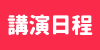 |
 |
|||
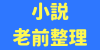 |
◆「老前整理」は、(株)くらしかるの登録商標です。無断での商用利用はお断りします。